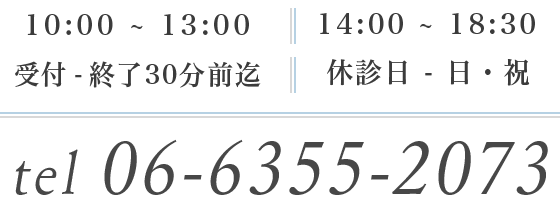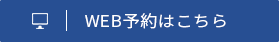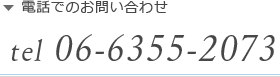睡眠時無呼吸症候群と事故
2015年12月28日
こんにちは 院長の市来です。
今回は睡眠時無呼吸症候群と事故について書きたいと思います。
現在、仕事としてトラック、バス、タクシー、鉄道、船、飛行機など運転する人は、日本には300万人以上もおります。肥満の人や男性は、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすい傾向にありますが、職業として運転している人には肥満傾向の男性が多く、睡眠時無呼吸症候群の発症リスクが高いとされています。しかも発症リスクが高いのに職業運転者は睡眠時無呼吸症候群の自覚症状が乏しい傾向にあります。過去にトラック運転者2万人に対しておこなった大規模な調査によると、中~重症の睡眠呼吸障害があると診断されたトラック運転者の86%が、眠気などの自覚症状に乏しいという結果がでました。
AHI(1時間当りの無呼吸および低呼吸の回数)が10以上で居眠り事故を起こす確率は6.3倍になります
多くの研究により、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、健常者よりも交通事故を引きおこす確率が高いことがわかっています。運転者の眠気を原因とする事故は、事故全体の10~30%を占めるとされています。
バスやトラックや車の居眠り運転事故は、ブレーキをふまないまま発生することが多いため、致死率が高い大きな事故になりやすい傾向にあります。
アメリカでの運転記録による実態調査では、睡眠時無呼吸症候群の患者さんの交通事故発生率は、健常者の約7倍も高いとのことです。
交通事故の発生率が高いのは、いびきや無呼吸によって睡眠の質が悪い結果、運転中に寝てしまったり、うとうとしてしまったり、注意力が低下するためです。同様の調査結果は、日本、カナダ、スペインなど世界各国から多数報告されています。
1979年のスリーマイル島の原子力発電所炉心融解未遂事故
1986年のスペースシャトルの発射直後の爆発事故
1989年のアラスカ沖のタンカー座礁(史上最悪のタンカー事故)
など大事故の原因に睡眠時無呼吸症候群が関連していると言われています。
日本における睡眠障害による経済損失は、医療費を含まない額で年3.5兆円と試算されています。かなり大きな損失です。
居眠りの予防策
ふだんから十分睡眠をとり、睡眠不足が生じないように、規則正しい生活習慣を心がけましょう。
睡眠時無呼吸症候群であれば、適切な治療をおこないましょう。
眠たくなったら、短時間(15~30分程度)の仮眠をとるようにします。30分以上の仮眠をとると、眠気がとれなくなることがあるので注意が必要です。
仮眠後は、身体を動かして十分覚醒させましょう。起きてすぐはまだ眠たさが残っています。
コーヒーなどのカフェイン飲料を上手に摂取しましょう。ただし、カフェインの効果が現れるのは、摂取してから30分後くらいです。
また、糖分の入ったカフェイン飲料の大量摂取は、肥満や睡眠時無呼吸症候群の症状悪化になるので注意が必要です。
ガムを食べたり、声を出したりしてアゴを運動させると、脳が活性化します。

酸蝕症について
2015年12月21日
こんにちは。
歯科医師の新井です。
今回は酸蝕症についてお話させていただきます。
柑橘類や梅干を食べる、ビタミンCの多い飲み物を飲む、ワインを飲むなどしたときに歯がきしむような経験をされたことはないでしょうか。そのようなときは一時的に飲食物に含まれる酸によりエナメル質が溶けてしまうからです。しかししばらくすると、そのきしむ感じはなくなります。それは唾液の力によって再石灰化が起こりもとどおりに修復されるからです。
しかし、長時間だらだら食べたり、摂取する頻度が多いと、唾液によって再石灰化される前にどんどん歯が溶けていくことがあります。これが酸蝕症といわれるものです。虫歯菌により歯が溶けるのではなく、飲食物の酸によって歯が溶けていくことになります。歯が溶けると、虫歯と同じように、歯がしみたり、噛んだときに痛いという症状がでることになります。
また、中には摂食障害などで嘔吐する癖がある方も、自身の胃酸で歯が溶けていくことがあります。
酸蝕症の予防法としては、酸性飲食物をだらだら食べたり飲んだりしない。
とくに寝る前に酸性飲食物を食べたり飲んだりしない。
就寝中は唾液分泌が少ないので歯の再石灰化が起こりにくいです。また、酸性飲食物をとった後はよくうがいをする。他には、酸性の飲食物を摂食したあとはすぐにブラッシングをしない。
酸性飲食物を多量に取るとエナメル質が柔らかくなっているので、すぐブラッシングすると歯が余計に削れます。
虫歯はなくても歯がしみる感じがする方は、日々の食生活を見直してみてはいかがでしょうか。

摂食・嚥下障害について
2015年12月14日
こんにちは。歯科医師の丸野です。
高齢化が進む今日の我が国におきまして、摂食・嚥下障害が問題視されています。今回は摂食・嚥下障害について説明させていただきます。
摂食・嚥下障害とは、口から食べる機能の障害のことを言います。人は無意識に食べ物を目や臭いで認識し、口まで運び、口に入れて噛み、飲み込むことで、食物や液体を摂取しています。以下がその細かな過程です。
①目で見て食べ物を認知する
②食べ物を口の中にいれて咀嚼する
③舌が食べ物を後ろ側に送り込む
④食べ物が咽頭を通過する
⑤食べ物が食道を通過する
摂食・嚥下障害とはこの5つのステージの1つまたは複数が何らかの原因で正常に機能しなくなった状態をいいます。
摂食・嚥下障害の原因として最も多いのが脳梗塞などの脳血管障害です。高齢者におきましては、加齢による筋力低下によって摂食・嚥下障害を発症しやすくなります。
摂食・嚥下障害で問題になるのは、
① 低栄養・脱水
② 誤嚥性肺炎、窒息
③ 楽しみの喪失
です。症状の重さにもよりますが、正しい評価のもと、必要で効果的なリハビリを行い、正しい食事方法を選択することが重要です。
続いて治療法についてです。以下に主な治療法を挙げます。
1、嚥下訓練
安全な「食べ方」を身につける訓練や食事は使わず、「力」を鍛える訓練を患者様に合わせて指導します。
2、口腔内装置
舌を切除した方、舌の動きが悪い方などを対象に飲み込みを助ける装置を作製します。
3、栄養指導
口から全量栄養摂取が困難な方には経管栄養法を指導します。
4、食習慣の指導
料理方法の工夫や食事時の姿勢など、より安全に楽しく食事できるよう指導します。
以上のように、我々歯科医療関係者やその他の職種の方々と連携をとり、高齢者のQOLを高め、より良い良い地域社会が築かれること願っております。

歯のはえかわりについて
2015年12月8日
こんにちは、藤林です。
今回は子供の歯のはえかわりについて書かせていただきます。よくご質問頂くことについて書きますので、参考になさってください。
・子供の下の前歯の内側に大人の歯がはえてはじめてきた、これって大丈夫?
→特に問題ない場合が多いです。歯は舌の力と唇の力が釣り合いのとれる場所にはえてきますので、最終的に大人の歯は舌の力によってだんだん唇側に倒れるようにはえてくることが多いです。
ただ、顎が小さく歯がはえるスペースがなく、重なってはえてきている場合もありますので、心配に思ったらご相談下さい。また、大人の歯がだいぶはえてきても子供の歯が揺れてこない場合も問題がでてきますので、ご相談ください。
・大人の歯が黄色っぽい気がするんだけど…?
→子供の歯は白は白でも、青白がかってますので、それと比べるとどうしても大人の歯は黄色っぽく見えてしまいます。特に問題ないです。
・はえてきた歯がギザギザしている気がするけど…?
→もともとの大人の歯の形は先はギザギザしています。それが大人になり使ってすり減っていくことにより、平坦になってしまうだけで、もともとはギザギザしています。問題ありません。
・抜けたのに歯がはえてこないんだけど…
→子供の歯が抜けてからも大人の歯がはえてくるまで、期間を要す場合があります。まずは歯医者さんでレントゲンを撮って、大人の歯がちゃんとあるかどうか等確認してもらいましょう。

口内炎について
2015年12月4日
こんにちは。
歯科医師の新井です。
今回は口内炎についてお話させていただきます。
口内炎やは、体調が疲れていたり風邪をひいて抵抗力が弱まっているときにできやすいもので、ちょっとした粘膜の刺激だけでもできる場合があります。
口内炎を起こしにくくし、治りやすくするために重要な栄養素はビタミンB2とビタミンCです。
ビタミンCはよく耳にすると思いますが、ビタミンB2はどんな食品に含まれているのか見てみましょう。
ビタミンB2はうなぎやレバー、青魚に多く含まれているます。意外と摂りやすいのは魚肉ソーセージで、これならお子さまでも無理なく食べられます。
もちろん、栄養だけを摂取していればいいというわけではありませんので、体調をいい状態にキープし、お口の中も清潔に保つようにしてくださいね。